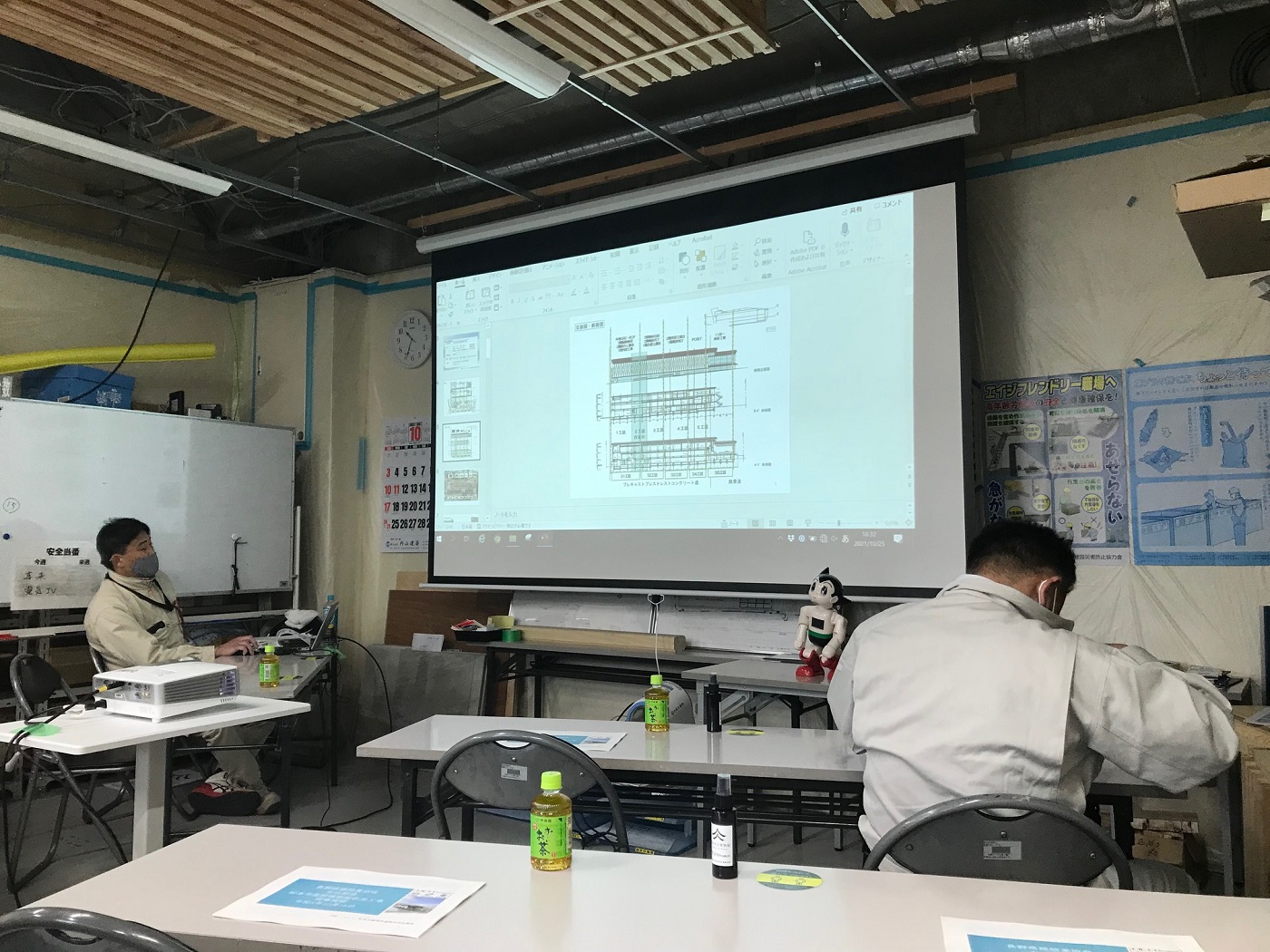令和7年5月12日、長野県建設業協会女性部会による現場見学会が開催されました。今回の見学では、山共建設が手がける古民家再生建築工事を学ぶ機会として、多くの女性部員が参加しました。
見学会では、まず当社会長による座学講習が行われ、「民家再生とは何か」について、実例を交えながら丁寧に解説。参加者からは熱心にうなずく姿も多く見られました。
続いて、実際に施工が進められている古民家再生現場を訪問。長年の時を刻んだ古材梁や建築技術の工夫に、普段は土木現場で活躍する女性部員たちも目を見張っていました。
参加者からは「普段とは違う分野の現場に触れる貴重な体験になった」「伝統建築の奥深さを感じた」といった声が寄せられ、建設業における学びと視野を広げる一日となりました。